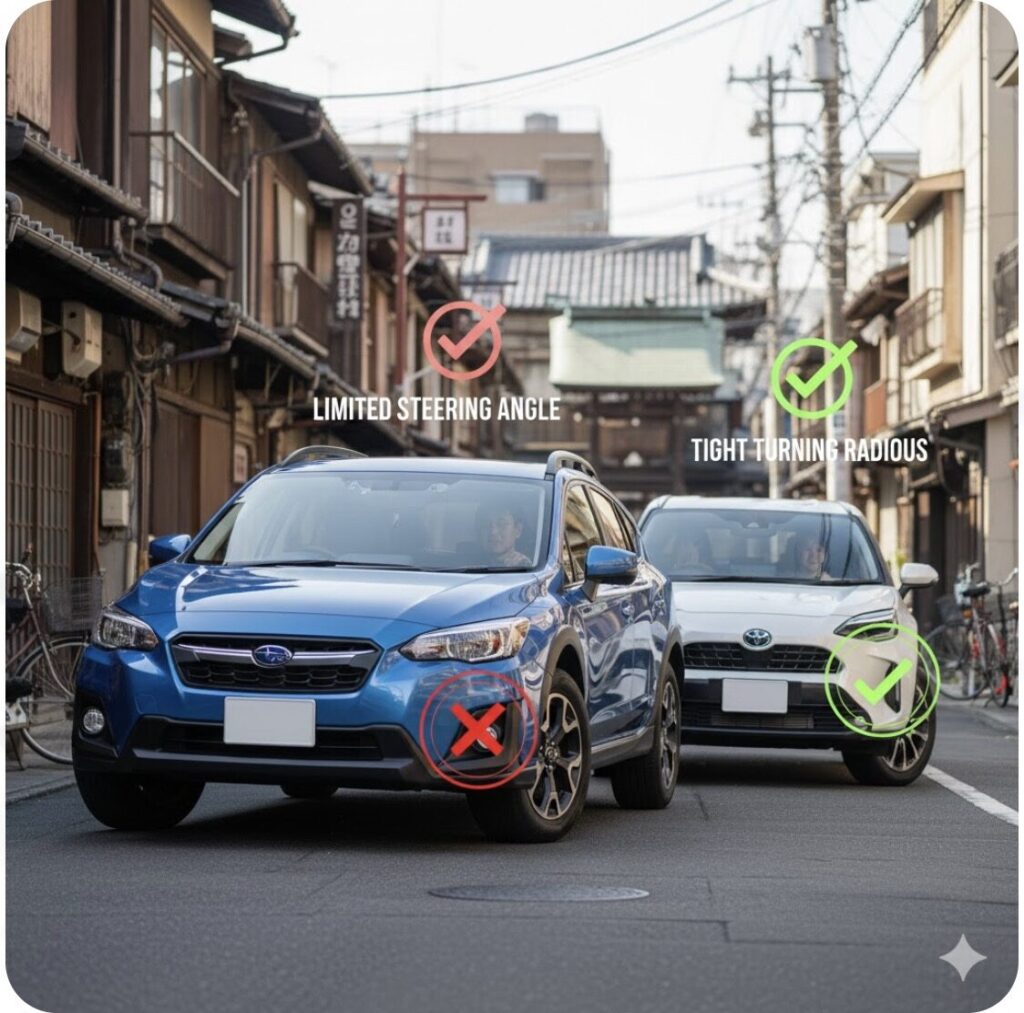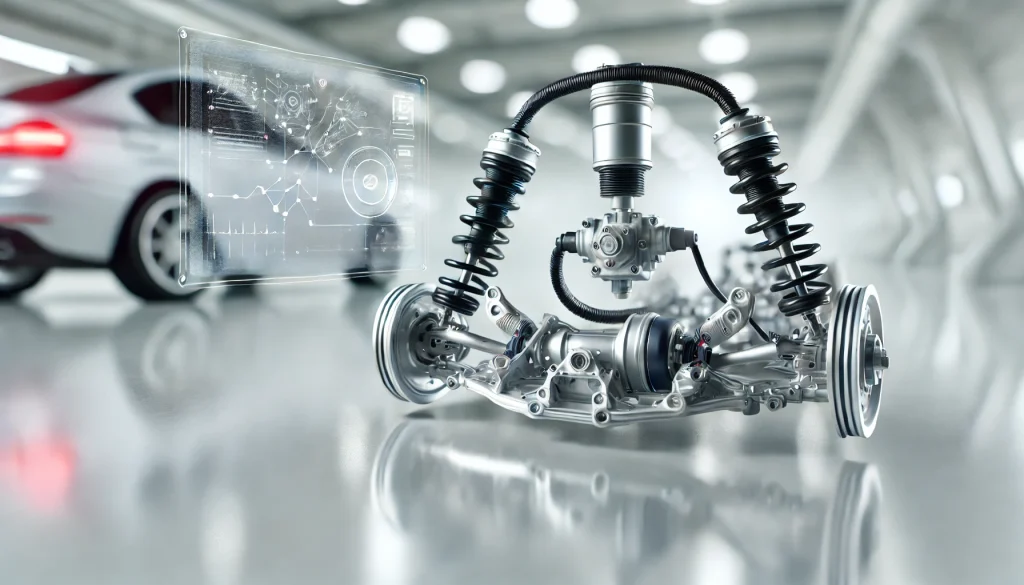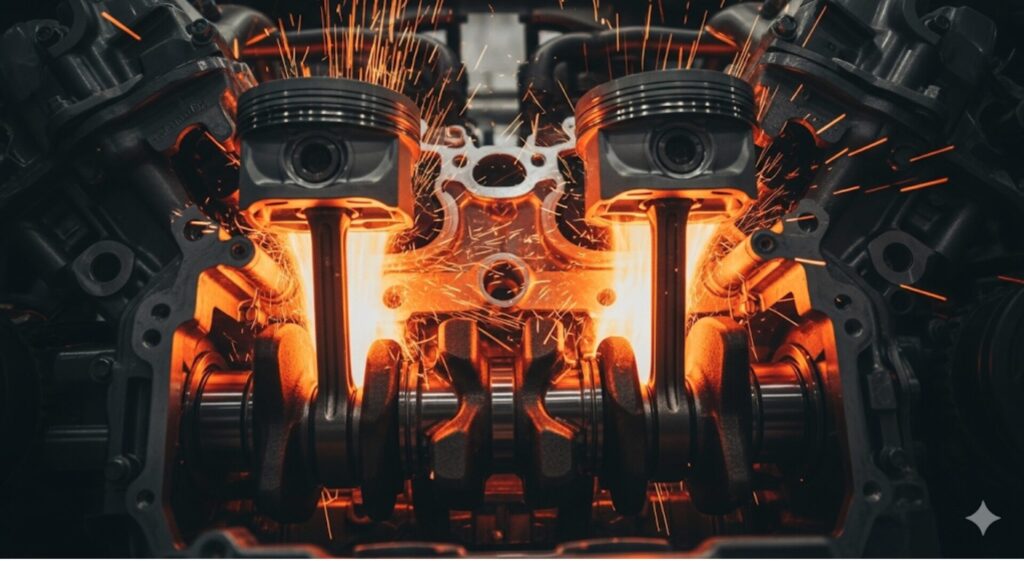ハイブリッド車や電気自動車の普及に伴い、「回生ブレーキ」という言葉を耳にする機会が増えました。一方で、昔ながらの「エンジンブレーキ」との違いがよく分からない、という方も多いのではないでしょうか。この記事では、回生ブレーキとエンジンブレーキの違いについて、基本的な仕組みから分かりやすく解説します。
ハイブリッド車や電気自動車の普及に伴い、「回生ブレーキ」という言葉を耳にする機会が増えました。一方で、昔ながらの「エンジンブレーキ」との違いがよく分からない、という方も多いのではないでしょうか。この記事では、回生ブレーキとエンジンブレーキの違いについて、基本的な仕組みから分かりやすく解説します。
エンジンブレーキとは何か、そして回生ブレーキとはどのような仕組みなのか。それぞれの定義から、回生ブレーキのやり方、気になるデメリット、時々話題になるカックンという乗り心地の問題まで掘り下げていきます。さらに、ハイブリッドのエンジンブレーキが弱いと感じる理由や、エンジンブレーキを使って充電ができるのかという疑問、そして少し専門的な回生ブレーキと回生協調ブレーキの違いにも触れていきます。この記事を読めば、あなたのブレーキに関する疑問がきっと解決するはずです。
この記事で分かること
- 回生ブレーキとエンジンブレーキの根本的な仕組みの違い
- それぞれのブレーキが持つメリットとデメリット
- 車種や状況に応じた効果的なブレーキの使い方
- 燃費や電費の向上につながるエコドライブのコツ
基本的な回生ブレーキとエンジンブレーキの違い

- そもそもエンジンブレーキとは?
- エネルギーを再利用する回生ブレーキとは?
- 回生ブレーキのデメリットと注意点
- なぜハイブリッドのエンジンブレーキは弱いのか
- 回生ブレーキでカックンと感じる原因
そもそもエンジンブレーキとは?
エンジンブレーキとは、主にガソリン車やディーゼル車などの内燃機関を搭載した自動車で使われる減速方法です。アクセルペダルから足を離したり、ギアを低い段(シフトダウン)に入れたりすることで作動します。
このとき、エンジン内部では燃料の供給が停止、あるいは大幅に減少します。しかし、タイヤの回転力によってエンジンは強制的に回され続けるため、ピストンが動く際の抵抗(ポンピングロス)や、エンジン内部の部品同士の摩擦抵抗が発生します。このエンジンが「回されまい」とする抵抗力が、車速を落とす力、すなわちエンジンブレーキとして作用するのです。
エネルギーの観点から見ると、エンジンブレーキは車の持つ運動エネルギーを、主にエンジン内部の摩擦による熱エネルギーに変換して大気中に放出しています。つまり、エネルギーを再利用することなく、減速のためだけに消費しているのが特徴です。
豆知識:長い下り坂で活躍
特に長い下り坂では、フットブレーキ(摩擦ブレーキ)を多用すると、ブレーキパッドやディスクが高温になりすぎてブレーキが効かなくなる「フェード現象」や「ベーパーロック現象」を引き起こす危険があります。エンジンブレーキは、このフットブレーキの負担を軽減し、安全に坂道を下るための重要な補助ブレーキとして活躍します。
エネルギーを再利用する回生ブレーキとは?

回生ブレーキは、電気自動車(EV)やハイブリッド車(HV)、プラグインハイブリッド車(PHEV)など、モーターを動力源として利用する車両に搭載されている減速システムです。「回生」とは「生き返らせる」という意味で、その名の通り、減速時に捨てられていたエネルギーを回収して再利用する画期的な仕組みです。
具体的には、ドライバーがアクセルペダルから足を離したり、ブレーキペダルを軽く踏んだりすると、それまでタイヤを駆動させていたモーターが、逆にタイヤの回転力によって回されることで発電機としての役割に切り替わります。このとき、発電するために大きな抵抗力が必要となり、その抵抗力が車の減速力となるのです。
そして、この発電によって生み出された電気エネルギーは、バッテリーに充電され、次の加速時などに再びモーターを動かすための電力として再利用されます。
このように、回生ブレーキは運動エネルギーを電気エネルギーに変換して回収・再利用するため、エネルギー効率を大幅に向上させ、燃費(電費)の改善に大きく貢献する、環境に優しいブレーキシステムと言えます。
| 項目 | エンジンブレーキ | 回生ブレーキ |
|---|---|---|
| 主な搭載車種 | ガソリン車、ディーゼル車 | 電気自動車(EV)、ハイブリッド車(HV) |
| 仕組み | エンジンの回転抵抗を利用 | モーターを発電機として利用 |
| エネルギー変換 | 運動エネルギー → 熱エネルギー | 運動エネルギー → 電気エネルギー |
| エネルギー利用 | 放出(捨てる) | 回収・再利用(充電) |
回生ブレーキのデメリットと注意点

エネルギー効率に優れる回生ブレーキですが、いくつかのデメリットや注意点も存在します。これらを理解しておくことで、より安全で快適な運転が可能になります。
回生ブレーキが効かない・弱まるケース
1. バッテリーが満充電の時
回生ブレーキは発電した電気をバッテリーに蓄える仕組みのため、バッテリーが満充電の状態では、それ以上電気を蓄えることができず、回生ブレーキが作動しなくなります。長い下り坂が続くような場面では、下り始める前にバッテリー残量をある程度減らしておくか、フットブレーキや(車種によっては)エンジンブレーキを併用する必要があります。
2. 低温時
リチウムイオンバッテリーは低温時に性能が低下し、電気の受け入れ能力が落ちる特性があります。このため、冬場の寒い日などには回生ブレーキの効きが通常よりも弱まることがあります。
3. 滑りやすい路面
回生ブレーキは駆動輪にのみ作用するため、雨や雪で濡れた滑りやすい路面で強く効かせすぎると、タイヤがスリップする原因となる可能性があります。ただし、最近の車はABS(アンチロック・ブレーキ・システム)などと協調制御されているため、過度に心配する必要は少なくなっています。
また、回生ブレーキの効き具合はメーカーや車種によって大きく異なるため、初めて乗る車の場合は、その特性に慣れるまで慎重な運転を心がけることが大切です。
なぜハイブリッドのエンジンブレーキは弱いのか

ハイブリッド車に乗っていると、「ガソリン車に比べてエンジンブレーキの効きが弱い」と感じることがあります。これにはいくつかの理由が関係しています。
第一に、現代のハイブリッド車に搭載されているエンジンは、燃費性能を追求するために、エンジン内部の摩擦抵抗(フリクションロス)が極限まで低減されていることが挙げられます。エンジンブレーキは、この内部抵抗を利用して減速力を得るため、もともとの抵抗が少なければ、当然ブレーキの効きもマイルドになります。これは最新の低燃費ガソリン車にも共通する傾向です。
第二に、ハイブリッドシステムの構造が関係しています。特にトヨタのハイブリッドシステム(THS)の場合、アクセルオフ時の減速は、主にモーターによる回生ブレーキが担っています。ドライバーがエンジンブレーキとして操作する「Bレンジ」に入れても、バッテリー残量に余裕がある状況では、エンジンを始動させずに回生ブレーキを強く効かせる制御が行われることが多いです。純粋なエンジンブレーキがかかるのは、バッテリーが満充電に近い場合や、一定以上の速度域など、特定の条件に限られます。

日産のe-POWERのように、エンジンを発電専用とし、駆動は100%モーターで行うシリーズハイブリッド方式の車には、そもそも構造としてエンジンブレーキが存在しません。これらの車種では、アクセルオフ時の減速力はすべて回生ブレーキによって生み出されています。
これらの理由から、多くのハイブリッド車ではガソリン車のような強いエンジンブレーキ力が体感しにくくなっているのです。
回生ブレーキでカックンと感じる原因

電気自動車やハイブリッド車で、停止する直前に「カックン」と前のめりになるような、不自然な揺れを感じたことはありませんか。この現象は、回生ブレーキ特有の乗り心地の問題として時々指摘されます。
この「カックンブレーキ」の主な原因は、回生ブレーキと、従来の摩擦ブレーキ(油圧ブレーキ)との切り替え制御の難しさにあります。
車が完全に停止するためには、最終的にタイヤの回転を物理的に止める摩擦ブレーキが必要です。回生ブレーキは、タイヤが回転していることで発電・減速するため、ごく低速域になると効果が著しく低下し、完全停止はできません。
そのため、減速の大部分を回生ブレーキで行い、停止寸前で摩擦ブレーキにバトンタッチするという制御が行われます。このバトンタッチがスムーズに行われないと、2種類のブレーキの制動力の差が衝撃となり、「カックン」という不快な挙動として現れてしまうのです。
ワンペダル操作も一因に
日産リーフの「e-Pedal」のように、アクセルペダルの操作だけで発進から停止まで行える「ワンペダル機能」を搭載した車種もあります。この機能はペダルの踏み替えが減り非常に便利ですが、アクセルを離した際の回生ブレーキが強く設定されているため、慣れないうちはペダル操作がラフになり、カックンブレーキを誘発しやすい側面もあります。
ただし、メーカー各社はこの課題を認識しており、年々制御技術は進化しています。特にトヨタの「回生協調ブレーキ」のように、2つのブレーキをより緻密に連携させることで、非常に滑らかな乗り心地を実現している車種も増えています。
実践でわかる回生ブレーキとエンジンブレーキの違い

- 効果的な回生ブレーキのやり方
- ハイブリッドのエンジンブレーキで充電できる?
- 回生ブレーキと回生協調ブレーキの違い
- メーカーで異なる回生ブレーキの操作方法
- まとめ:回生ブレーキとエンジンブレーキの違いを理解しよう
効果的な回生ブレーキのやり方
回生ブレーキの特性を理解し、少し運転方法を意識するだけで、エネルギーの回収効率を高め、燃費(電費)を向上させることができます。特別な操作は必要なく、エコドライブの基本と同じです。
回生効率を高める3つのポイント
1. 早めのアクセルオフを心がける
前方の信号が赤に変わった時や、渋滞の最後尾が見えた時など、停止することが予測できたら、できるだけ早くアクセルペダルから足を離すのが最も重要です。これにより、回生ブレーキが作動する時間が長くなり、より多くのエネルギーを回収できます。
2. ブレーキは「じわっと」踏む
急ブレーキを踏むと、システムは危険を回避するために摩擦ブレーキを強く作動させ、回生ブレーキの割合が減ってしまいます。停止する際は、ブレーキペダルを「じわっと」緩やかに踏み込むことで、回生ブレーキを最大限に活用しながらスムーズに減速できます。
3. 車間距離に余裕を持つ
前の車との車間距離を十分に保つことは、安全運転の基本であると同時に、エコドライブの秘訣でもあります。車間距離に余裕があれば、前の車の急な動きに慌てる必要がなくなり、無駄な加減速が減ります。結果として、上記1、2のような緩やかな減速操作がしやすくなり、回生効率が高まります。
つまり、「急」がつく操作(急加速・急減速)を避け、速度変化の少ない滑らかな運転を心がけることが、回生ブレーキを最も効果的に使うやり方と言えるのです。
ハイブリッドのエンジンブレーキで充電できる?

「ハイブリッド車のBレンジ(エンジンブレーキモード)を使えば、充電しながら減速できるのか?」これは多くの方が抱く疑問ですが、答えは「車種や状況による」というのが実情です。
まず、トヨタのハイブリッドシステム(THS)を例に考えてみましょう。シフトポジションを「B」レンジに入れると、通常の「D」レンジでアクセルを離した時よりも強い減速力が得られます。
Bレンジの挙動
- バッテリーに空きがある場合:この時の減速力の多くは、モーターによる回生ブレーキを強めることで生み出されます。そのため、結果的にバッテリーは充電されます。
- バッテリーが満充電に近い場合:回生ブレーキが使えないため、システムは強制的にエンジンを始動させ、その回転抵抗を利用した純粋なエンジンブレーキをかけます。この場合、エンジンが回ることでガソリンをわずかに消費したり、エネルギーを熱として捨てたりするため、充電効率は良くありません。
つまり、トヨタのハイブリッド車では、Bレンジは必ずしもエンジンブレーキを使っているわけではなく、状況に応じて回生ブレーキとエンジンブレーキを使い分けているのです。燃費を最優先するなら、Bレンジは使わずにフットブレーキを緩やかに踏んで回生量を稼ぐ方が有利な場合が多いとされています。

では、Bレンジはいつ使うのが効果的なのでしょうか? 答えは、バッテリーが満充電になってしまいそうな、非常に長い下り坂です。回生ブレーキが効かなくなった後も安定した減速力を確保し、フットブレーキの負担を減らすためにBレンジが役立ちます。
一方、日産のe-POWERのようにエンジンが発電に徹しているシステムでは、Bレンジ(またはECOモード)で得られる減速力はすべて回生ブレーキによるものです。この場合は「Bレンジを使う=積極的に充電する」と考えることができます。
回生ブレーキと回生協調ブレーキの違い

回生ブレーキを語る上で欠かせないのが、特にトヨタやホンダが得意とする「回生協調ブレーキ」という先進的な技術です。
「回生ブレーキ」がモーターを発電機として利用する減速方法そのものを指すのに対し、「回生協調ブレーキ」は、その回生ブレーキと従来の摩擦ブレーキ(油圧ブレーキ)を、ドライバーに違和感なく、かつ最も効率的に連携(協調)させる制御システムのことを指します。
ブレーキペダルが踏まれると、車両のコンピューターはドライバーがどれくらいの減速力を求めているかを瞬時に計算します。そして、その要求された制動力のうち、可能な限り多くの部分をまず回生ブレーキで賄おうとします。
しかし、回生ブレーキだけで必要な制動力が得られない場合(急ブレーキ時やバッテリー満充電時など)や、車が停止する直前の極低速域では、不足分を補う形で摩擦ブレーキが自動的に介入します。この2つのブレーキの強弱バランスを、1ミリ秒単位で緻密にコントロールすることで、以下のようなメリットが生まれます。
回生協調ブレーキのメリット
- エネルギー回収の最大化:常に回生ブレーキを優先するため、エネルギーの回収効率が非常に高まります。
- スムーズなブレーキフィール:2つのブレーキの切り替わりを感じさせない、滑らかで自然なブレーキ感覚を実現します。
- ブレーキパッドの長寿命化:摩擦ブレーキの使用頻度が減るため、ブレーキパッドの摩耗が少なくなり、メンテナンスコストの削減に繋がります。
この回生協調ブレーキの制御技術の高さが、近年のハイブリッド車や電気自動車の乗り心地と燃費性能を大きく向上させているのです。
メーカーで異なる回生ブレーキの操作方法
回生ブレーキの強さやその操作方法は、自動車メーカーの設計思想によって異なり、それぞれの車種にユニークな特徴を与えています。ここでは代表的な例をいくつか紹介します。
日産:e-Pedal(ワンペダル操作)
日産の「リーフ」や「ノート e-POWER」などに搭載されている「e-Pedal」は、アクセルペダルの操作だけで加速から減速、さらには完全停止(一部車種を除く)までコントロールできる画期的な機能です。アクセルを離すだけで強い回生ブレーキがかかり、ブレーキペダルへの踏み替え回数が大幅に減るため、運転疲労の軽減や、踏み間違いリスクの低減に繋がります。
三菱:回生レベルセレクター(パドルシフト)
三菱の「アウトランダーPHEV」などでは、ステアリングに備えられたパドルシフトで回生ブレーキの強さをドライバーが任意に選択できます。多くの場合、複数段階(例:6段階)のレベルが用意されており、回生を全く効かせずに惰性で走る「コースティング」から、強いエンジンブレーキのような減速まで、走行シーンに合わせて好みの強さを選べるのが特徴です。運転を積極的に楽しみたいユーザーから高い評価を得ています。
トヨタ:Bレンジと協調制御
トヨタの多くのハイブリッド車は、前述の通り「Bレンジ」で強い減速力を得られるように設計されています。しかし、トヨタの思想の根幹にあるのは、ドライバーに特別な操作を意識させない「回生協調ブレーキ」です。通常はDレンジのまま、ごく自然なブレーキペダルの操作を行うだけで、システムが自動的に最も効率的なエネルギー回収を行ってくれるため、誰でも簡単にエコドライブが実践できるのが強みです。

このように、一口に回生ブレーキと言っても、その操作方法や乗り味は様々です。ワンペダルで楽に運転したいのか、パドルシフトで積極的に操作したいのか、あるいは車に任せて自然に乗りたいのか。こうした回生ブレーキの特性に注目して、次の愛車を選んでみるのも面白いかもしれませんね。
まとめ:回生ブレーキとエンジンブレーキの違い
この記事では、回生ブレーキとエンジンブレーキの違いについて、仕組みから使い方、メーカーごとの特徴まで詳しく解説しました。最後に、本記事の重要なポイントをリストで振り返ります。
- エンジンブレーキはエンジンの回転抵抗を利用して減速する仕組み
- 回生ブレーキはモーターを発電機として使い運動エネルギーを電気に変える
- エンジンブレーキのエネルギーは熱として捨てられる
- 回生ブレーキのエネルギーは充電され再利用される
- 回生ブレーキはバッテリー満充電時や低温時に効きが弱まる
- ハイブリッド車のエンジンブレーキが弱いのはエンジンの低抵抗化が理由
- カックンブレーキは回生と摩擦ブレーキの切り替えが原因
- 効果的な回生ブレーキのやり方は緩やかでスムーズな減速
- ハイブリッド車のBレンジは状況により回生とエンブレを使い分ける
- 回生協調ブレーキは回生と摩擦ブレーキを最適に連携させる制御システム
- 回生協調ブレーキはエネルギー回収効率と乗り心地を両立させる
- 日産のe-Pedalはワンペダルでの運転を可能にする
- 三菱のパドルシフトは回生レベルを任意に調整できる
- トヨタは自然な操作で効率的な回生を行う協調制御を重視
- それぞれのブレーキの特性を理解することが安全でエコな運転につながる